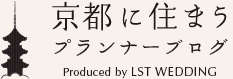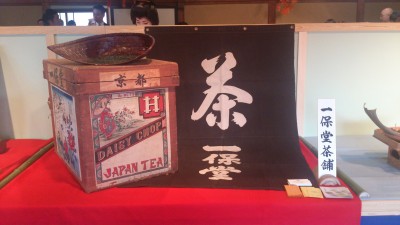2014月3月の記事 一覧
京都 時代祭
10月22日、京都の3大祭りのひとつ
「時代祭」が繰り広げられました。
「時代祭の歴史」
時代祭は平安神宮の創造と平安遷都1100年を記念する
行事として,明治28年に始まりました。
明治維新後 、活気を失った
京都の町おこしのため、平安神宮は創造され、
その思いとともに、京都の人々が
「京都でしかできないことを 」「一目で歴史がわかるものを」
と時代祭を始められました。
・約2000人による時代絵巻物です
また、平安神宮のご祭神の桓武天皇 、
考明天皇のご神霊に巡行して頂き、現代の京都をご覧頂く祭礼で、
時代行列は神幸列にお供する祭列です。
人々が町の平和を祈る思いが込められています。
歴史を知り、行事に触れたり、町を歩くと
京都の新しい魅力に気づきます。
LSTウエディング 西川 徳子
京都 鱧の文化
祇園祭りの時期、
京料理にかかせない、「鱧」。
生命力が強い鱧は、
昔、山々に囲まれている京都へ暑い時期に運ばれる
魚の中でも特に鱧が強く、重宝がられたそうです。
また、京都の一部の地域では
自宅でこしらえた、鯖寿司をもってご挨拶に伺い、
ご挨拶を受けた側は鱧寿司を用意するという習慣あったそうで、
お中元に鱧寿司を贈るのはその名残が残っています
【京料理 木乃婦さん】
本日、木乃婦さんよりお中元で「鱧寿司」を頂戴いたしました。
いつもお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。

今の時期に最高の食材で、鱧をいただくと、初夏を感じます。
鱧は、古くから京都に根付いており、
京の食文化にはたいせつな食材です。
都をどり
4月も下旬、やっと、「都をどり」を見に行きました。
4月1日〜30日まで歌舞練場で行われる、都をどり。
驚いたのは、お客様のほぼ半分の方が、海外からお越しのお客様だったことです。
〜都をどりの歴史〜
明治維新による東京への遷都の際に、京都の人々が京の都の衰退を恐れ、
当時(明治4年)京都知事らが再建に奔走し、京都での博覧会計画を立てました。
祇園万亭(現一力亭)の主人杉浦治郎右衞門に意見を求め、
春季の博覧会の附博覧(つけはくらん:余興の意)として、
祇園の芸舞妓のお茶と歌舞を公開したことがはじまりです。
芸・舞妓さんの舞。
京都友禅のお着物、髪飾り。地方さんの御三味線。
観て、聞いて、その場にいるだけで京都文化が楽しめる、素晴らしい舞台です。
また、来年も見に行きたいです。