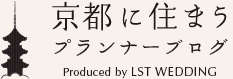15日、20時八坂神社さんにて「宵宮祭」が行われました。
本殿でのお祓いや祝詞奏上などの儀式が行われた後、
全ての灯りが消され、御霊を御神輿に移します。
本殿より、白装束の神職の方が大きな白い布に御霊をおおい、舞殿に向われます。
中御座に素戔嗚尊(すさのをのみこと)、東御座に櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)、
西御座に八柱御子神(やはしらのみこがみ)の順に
御霊をうつされました。
本殿と舞殿の間は一般の方が入れないように結界がはられます

御霊が移された御神輿
17日の神輿渡御にて本殿を出発、四条御旅所に鎮座され
24日に御神輿が戻ってきた後に、御霊が本殿に移されます(御霊返し)


儀式中、台風の影響のためか風が吹き、提灯が大きく揺れていました。
17日の山鉾巡行、神幸祭までもう少し。
どうかすべての神事が無事行われますよう、
祈るばかりです。
LST 西川 徳子
四条烏丸に、堂々と佇む「長刀鉾」。
17日に行われる、山鉾巡行を待ち構えているかのようです。
鉾先の大長刀は疫病邪悪をはらうものとされ、
長刀鉾が必ず毎年、山鉾巡行の先頭にたち
生稚児の乗る鉾は、こちらの鉾のみです。

宵々山、宵山では四条界隈は歩行者天国になり、
お囃子やたくさんの出店で大盛り上がりの一方、
今夜(20時)に八坂神社さんで、
本殿から3つの神輿に御神霊をうつす「宵宮祭」が行われます。
境内の灯りをすべて消し、行われるこの儀式はとても神秘的です。
こちらも見逃せません(^^)
LST 西川 徳子
10日の夜、八坂さんから3基の代表の
お神輿(中御座)が四条まで担ぎ出され、
朝に清められた神水で神輿洗が行われました。
お神輿に川の神様をお迎えしたのです。
神水を降りかかることにより、
厄除けや病から身を守るといわれています。

八坂さんに帰ってくる、 「お迎え提灯」のみなさん。
(「お迎え提灯」とは、お神輿を迎えるための提灯の行列を意味します)
7月らしく蒸し暑い1日となった今日、子供たちは本当に頑張られました!
武者姿、着物姿の子供たちがとっても可愛いです。


神輿洗を終えた、お神輿(中御座)も八坂さんに戻ってきました。
この後、17日の神輿渡御にむけて飾りつけられます。


画像が見えずらく、申し訳ありません。
少しでも、雰囲気がお伝えできればと思い
お写真をご紹介させていただきました。
これからが本番の祇園祭です!
LSTウエディング 西川 徳子
7月10日、祇園祭の大事な神事の一つである、「神輿洗」の準備が始まりました。
「神輿洗」とは17日神幸祭、24日環幸祭の神輿渡御のために御神輿を清める儀式です。
「神用水清祓式」〜鴨川の神様をお迎えします〜
10時、四条鴨川にて、夜の神輿洗に使うお水が
宮本組より汲み上げられます

儀式中、雅楽が鳴り響き、これが「神事」なんだと実感させられます

汲み上げられた水が清められます
約30分行われた儀式、見ているだけでも汗ばみました。
紋付姿の宮本組、雅楽の方は相当暑いに違いありません。

この儀式は本来、ただ神輿を清め祓うのみでなく、
かつて、京都が盆地湿地帯で
鴨川の洪水による疫病を恐れたため、
鴨川の神様を神輿にお招きし、祇園社にお迎えすることにより、
神様にお鎮まりいただくという祈りも込められていたそうです。
本日(10日)は同時に鉾も準備が始まりました。
氏子の人々が神様を歓迎し、通られる道を清める「お迎え提灯」
大松明による「道しらべの儀」、
そして「神輿洗」とつづきます。
本当に多くの人々によって、この祇園祭が支えられているという事を
感じずにはいられない1日です。
LST 西川 徳子
祇園祭では山鉾巡行がとても有名ですが、本来は御神輿が主役。
京都の祭礼では、神輿の行く手を剣鉾(悪霊を沈める祭具)が祓い清め、
そこへ御神輿が巡行するのがならわし。
ですので、山鉾巡行は剣鉾が巨大になった行列で、
御神輿が通る道を清める意味があります。
○7月10日 神輿洗(みこしあらい)
17日、24日の神輿渡御のため御神輿を清める儀式
○7月17日 山鉾巡行(やまぼこじゅんこう)
鉾の巡行により、御神輿が通る道を清めます
神幸祭(しんこうさい)
八坂神社の3人の祭神が御神輿に乗って、氏子町内を渡幸されます
四条御度所にて1週間鎮座されます
○7月24日 環幸祭(かんこうさい)
八坂神社の3人の祭神が御神輿に乗って環幸されます
3つの御神輿
中御座 素戔嗚尊 (すさのをのみこと) ・ 東御座 櫛稲田姫命 (くしいなだひめのみこと)
西御座 八柱御子神 (やはしらのみこがみ)
約1000人の氏子により担がれます 本当に圧巻です(^^)

長刀鉾
伝統的な装飾が施され、動く美術館と言われています

当然ながら、昔は、天災や災害が現代のように科学で証明できない時代、
神様の力を信じた時代だったからこそ
人々は悪霊を恐れ、平和に暮らせるよう、祈りを捧げたのです。
1000年以上、八坂神社の氏子組織、関わる人々の奉仕活動にて
儀式が継承されつづけました。
京のまちを思い、平和を祈る心が、
祇園祭を支え続けている理由に、他ならないと思います。
LST 西川 徳子
祇園祭の祭事を取り仕切る、
「宮本組」の存在をご存知でしょうか。
明治初頭に、八坂神社の氏子区域全域(旧25学区)からなる組織で、
中でも、宮本組は
神社のお膝元の弥栄地区に代々住まい、
熱心に神社に奉仕していた深いご縁をもつ人々です。
7月10日、祇園祭で重要な神事、「神輿洗」のため
四条大橋の鴨川の水をくみ上げる、宮本組。

17日、24日に行われる神輿渡御で
勅版(ちょくばん)や武器、楽器の御神宝を持ち御神輿を先頭。
この御神宝を触れるのも運ぶのも、宮本組のみが許されているそうです。

(平安時代、ご神体と神様が身につける御神宝と御装束は
一緒に巡行していたとう儀式が祇園祭では受け継がれています)
お仕事で尊敬している方が宮本組におられ、歴史を調べていくうちに、
ますます、祇園祭を深く知りたいと思うようになりました。(^-^)
是非とも機会あればご注目くださいませ。
LST 西川 徳子
いよいよ、7月。
京都「祇園祭」が始まりました。
1日の「吉符入り」から31日の「疫神社夏越祭」の1ヶ月間、
さまざまな神事、行事が執り行われます。
〜祇園祭〜
貞観11年(869)に京の都をはじめ全国に流行した疫病をおさめるため、
広大な神泉苑に、当時の66ヶ国にちなんで、
66本の鉾を立て祇園の神を祀り、御神輿を送ったことがはじまりです。
以来、1000年にも渡り、京の人々が守り続けています。
(当時の神泉苑は今現在のものより、かなり大きかったそうです)

御神輿、鉾、子供の頃から、大好きな祇園祭。
祇園祭の素敵を皆様にこれから1ヶ月お届けいたします(^ー^)
LST 西川 徳子
5年以上ぶりに来させていただいた、
「京都ネーゼ」さん。
やっと、やっと行けました!
本当に美味しかった!(^ー^)
カウンターとテーブル計16席のお店は
すぐに満員になってしまうほど、人気のお店です。
会話の中で、さりげなく好みを聞き出してくださり、
さらっとお料理をご提案くださるシェフ。
あっさりといただける、「蛤と夏野菜のパスタ」

濃厚!「ゴルゴンゾーラのパスタ」

新鮮な素材、確かな技術と味。
次回もカウンター席で楽しみたいです。
LST 西川 徳子
今朝は清水寺さんへ参りました。
本日28日は、清水寺開創の起源である「音羽の滝」の
ご本尊の不動明王の縁日です。
朝7時より僧侶がそろい、読経が行われました。
【清水寺 本堂の舞台】


【音羽の滝】
創建以来、一度も枯れる事がない、清泉。
開山 延鎮上人(えんちんしょうにん)と開基 行叡居士(ぎょうえいこじ)が出会った
清水寺起源の場。

朝6時からろうそくをお供えされ、7時から読経が行われます

早朝にも関わらず、たくさんの参拝者がおられました。
私も清々しい朝を迎える事ができました(^^)
LST 西川 徳子